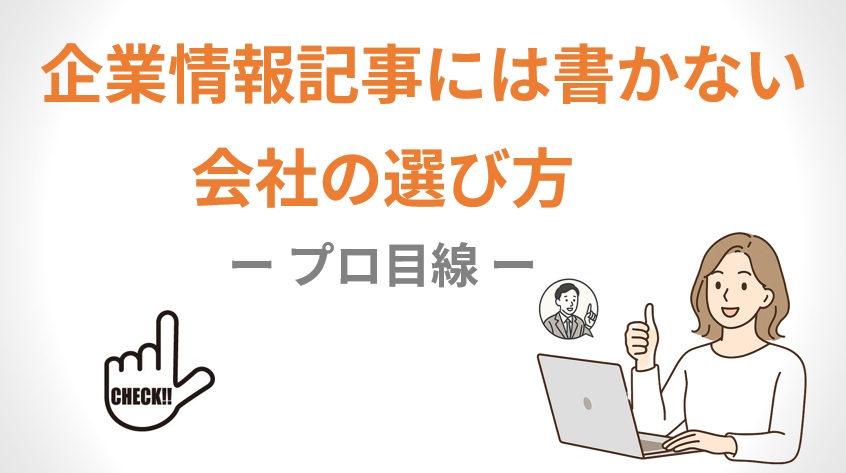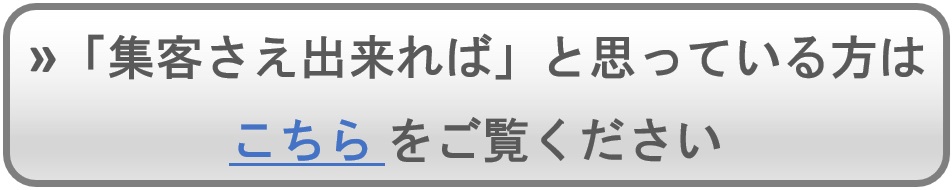この記事では、これらのことがわかります。
- 連鎖販売取引(ネットワークビジネス)とは何か
- ネットワークビジネスと特定商取引法の関係
- 気づかずに違反してしまうケース
- 違反が発覚した場合のリスクと対処法
- 法律を守りながらネットワークビジネスを続けるためのポイント
【用語解説】
MLM(ネットワークビジネス)とは、「Multi-Level Marketing(マルチレベルマーケティング)」の略で、複数階層に報酬が分配されるビジネスモデルのことです。
日本では一般的にネットワークビジネスと呼ばれることが多く、本記事ではこの名称を使って解説していきます。
目次
🌟特定商取引法の基本と、なぜネットワークビジネスで重要なのか
連鎖販売取引(ネットワークビジネス)は、商品やサービスを販売しながら、その紹介者(勧誘者)が新しい会員を勧誘し、報酬を得る仕組みです。
例えば、友人のAさんから「とても良いサプリメントだから一緒にやってみない?」と声をかけられた経験はありませんか?Aさんは、あなたが商品を購入したり、さらに他の人に紹介して購入してもらうことで、一定の報酬を得ることになります。
このビジネスモデル自体は法律違反ではありません。しかし、 特定商取引法(以下、特商法) によって、勧誘や販売の方法には厳しいルールが課されています。
MLM(ネットワークビジネス)を始めるとき、多くの方が「売れる方法」や「SNS集客」にばかり意識を向けがちですが、その前に大切なのが法律との付き合い方です。
中でも特定商取引法は、あなたのネットワークビジネス活動に大きく影響する法律。違反すれば知らなかったでは済まされず、あなた自身の信頼・活動・人間関係すら壊れてしまうことも。
この記事では、初心者が今のうちに知っておくべき重要チェック10項目をやさしく紹介します。詳細は別記事(実践編)で解説していますので、まずは全体像を掴んでください。
💬これだけは押さえたい!特商法チェック項目(概要紹介)
🔍1. 勧誘時の「事業内容説明義務」
ネットワークビジネスでは、勧誘の際に「これはネットワークビジネスです」と事業内容を正しく説明することが法律で義務付けられています。
相手に買い物や仕事の相談だと誤解させて話を進めると、重大な違法行為とみなされる可能性があります。
「最初に本題を明かす」ことは信頼構築の第一歩であり、健全な活動を続けるための基本です。
また、勧誘者は、相手に「これから勧誘を行うこと」を明示する必要があります。(勧誘時の事前告知義務)
🔍2. 書面交付義務(概要書面・契約書面)
ネットワークビジネスでは、勧誘時に「概要書面」、契約時に「契約書面」を紙で交付する義務があります。LINEやPDFではなく、法律上は“紙”が必要です。
この書面には事業内容や返品条件などが記載されており、相手が冷静に判断するための大切な資料です。未交付や不備があると、契約が無効になることもあります。
🔍3. クーリング・オフの説明義務
相手が契約後、冷静になって考え直せるようにするために「クーリング・オフ制度」があります。
これは契約後20日以内なら無条件で解約できる仕組みで、説明する義務があります。説明を怠ると制度自体が無効になる場合も。
誠実な勧誘を心がけるためにも、必ず正しく伝えましょう。
🔍4. SNSやDMでの誤認させる表現
SNSやDMでは、ネットワークビジネスであることを伏せた誘導や「楽して稼げる」「自由な生活」などの誇張表現が問題になります。
見る人が誤解するような投稿は特商法違反に該当することも。
ネット上の発信は証拠に残りやすいため、意図的なごまかしや過度な演出は避け、正直で丁寧な表現を心がけましょう。
🔍5. 所属会社・代表者などの明示義務
勧誘時には、所属する会社名・代表者氏名・所在地などの「販売者情報」を正しく伝える義務があります。
これは相手が会社の信頼性や契約の判断材料にするために必要な情報です。
これを伏せたり、曖昧にしたりすると違法となり、信頼も大きく損なわれてしまいます。事前に準備しておきましょう。
🔍6. 商品の価格・返品条件の明示(重要事項の説明義務)
「商品の価格」や「返品できるかどうか」などの取引条件は、契約前に正確に伝えなければなりません。
後から「そんな高いと思わなかった」「返品できると思っていた」とトラブルになるケースも多く、最悪の場合、勧誘そのものが無効とされる可能性も。
相手の立場に立った丁寧な説明を習慣にしましょう。
🔍7. 相手に誤解を与える収入の誇張
ネットワークビジネスでよく問題になるのが、「誰でも稼げる」「数か月で月収◯万」といった誇張された収入話です。
これらは相手に誤解を与え、現実とかけ離れている場合、違法になります。
実際は収入の個人差が大きく、誰にでも当てはまる話ではありません。
誠実な発信と“リアルな数字”が、長期的な信頼に繋がります。
🔍8. 公的機関を装ったような言い回し
「国も認めている」「厚労省が推奨している」といった表現は、公的機関を装った誤認行為として特商法違反となります。
たとえ事業が合法であっても、第三者の権威を借りて安心させる手法はNGです。
信頼は「誰が言ったか」ではなく「自分がどう説明したか」で築くものだと意識しましょう。
🔍9. 家族や第三者への説明不要と誘導する行為
「家族に内緒で契約しても大丈夫」「今決めた方が得」といった言動は、判断を急がせたり孤立させたりするため、法律で禁止されています。
特に高額商品や長期契約の場合、家族と相談してから契約するのが常識です。
無理に押し切るとトラブルに発展しやすく、あなた自身の信用にも関わります。
🔍10. 未成年・学生への契約時の特例ルール
未成年や学生との契約には特別な配慮が必要です。たとえ20歳を超えていても、親の承諾がないままの契約は後に取り消される可能性があります。
また、勧誘そのものが不適切とされる場合も。将来ある若者に不安を与えないよう、慎重に、そして誠実に接することがネットワークビジネス活動者としての責任です。
📌意外とやってしまいがちな違反例
1. 勧誘の意図を隠して話を進める
【ケース1】
美奈さん(32歳)は、育児休業中に友人の由美さんから「最近ハマっている美容サプリがあるんだけど、一緒に試してみない?」と声をかけられました。久しぶりに会ったこともあり、美奈さんは何気なく話に乗ってしまいました。
その後、何度か会ううちに「このサプリ、紹介するとお小遣い稼ぎになるんだよ」と説明され、気づけばビジネスに巻き込まれていました。
→ 違反ポイント: 勧誘の意図を隠して会話を進めるのは特商法違反です。
2. 誇大広告や過大な利益の約束
【ケース2】
会社員の恵子さん(35歳)は、同僚から「月収50万円も夢じゃないよ!」と誘われ、ネットワークビジネスを始めました。
しかし、実際には契約者を増やすことができず、赤字続き。
→ 違反ポイント: 「簡単に稼げる」と誤解を与える説明は、虚偽・誇大広告とみなされる可能性があります。
3. クーリング・オフの説明不足
【ケース3】
主婦の真由美さん(38歳)は、近所のママ友から「自宅でできるビジネスだから」と勧誘を受け、契約。
しかし、後になって「やっぱり辞めたい」と思ったものの、クーリング・オフの説明を受けていなかったため、解約の手続きがわかりませんでした。
→ 違反ポイント: クーリング・オフ制度の説明を省くのは大きな違反です。
4.オートシップの説明不足
【ケース4】
毎月、商品が届くこと、商品代金が銀行口座から引き落としされることを明確に伝えずにいると、本人に「聞いていなかった」「毎月、注文していない商品が届く」と不満や不信感が生じました。
→ 違反ポイント: 「重要事項の故意の不告知」という禁止行為の違反となります。特に「オートシップ」は「送り付け商法」と誤解される恐れがあります。「聞いた」「聞いていない」という誤解が起こらないように「伝えたつもり」で終わらないよう、確認作業が必要となることを肝に銘じましょう。
👉 犯罪を犯さぬよう、多岐におよぶ「意外とやってしまいがちな違反例」を【実践編】にてご確認ください。
違反が発覚した場合のリスク
もし特商法違反が発覚した場合、以下のようなリスクがあります。
- 行政処分や業務停止命令
- 罰金や損害賠償請求
- 信用の失墜やビジネス継続の困難さ
違反が発覚すると、自分だけでなく、紹介した相手にも影響が及ぶ可能性があります。
🎯まとめ
ネットワークビジネスでの活動を安心・安全に続けるためには、特定商取引法をしっかり理解し、誠実な勧誘を心がけることが不可欠です。
短期的な利益にとらわれず、長期的な信頼を築く姿勢が成功の鍵となります。
【実践編】にてご確認ください。
関連記事
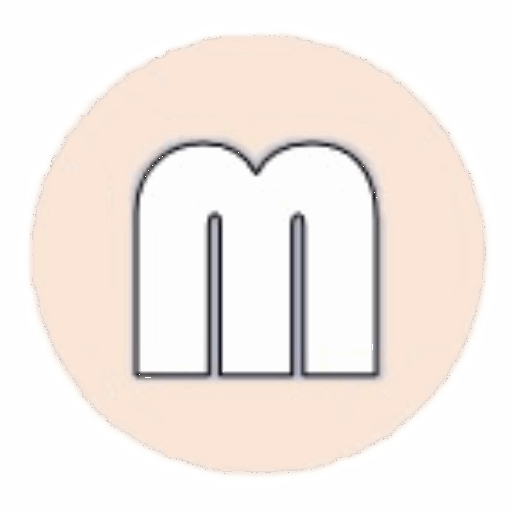 MLM研究所本部
MLM研究所本部 -940x525.jpg)